OUR MISSION
東京大学協創プラットフォーム開発、松尾研究所や著名起業家などによる
講義・フィールドワーク複合の実践的起業家育成講座
院生は、自身の研究内容や技術知見を生かし、事業会社との関わりや実経営において求められるマネジメント知見のインプットを通じて産業課題を解くことにチャレンジし、EXIT(M&A・IPO)を見据えた実践的なアントレプレナーシップの習得を目指します。
ニュース
-
2024.09.05
2024年度Aセメスター「ディープテック起業実践演習」の応募を開始しました。詳しくはこちら
-
2024.04.15
2024年度Sセメスター「ディープテック起業家への招待」の応募を締め切りました。
-
2024.03.17
2024年度Sセメスター「ディープテック起業家への招待」の応募を開始しました。詳しくはこちら
-
2024.03.17
2024年度S1ターム「ビジョナリー・スタートアップ~起業の理論と実践」の応募を開始しました。詳しくはこちら
-
2024.03.17
HPをリニューアルしました。
-
2022.06.17
工学部産学協創教育HP内に、本学アントレプレナーシップ関連講座検索システムをローンチしました。是非ご活用ください
-
2021.11.20
NHKより、本講座に関するニュースが掲載されました
-
2021.10.25
日本経済新聞より、本講座に関する記事が掲載されました
-
2021.08.19
プレスリリースを行いました。こちらからご覧ください
ABOUT
-
目指す姿
- 学部生は、長期的な未来を構想しながらビッグピクチャー(実態ある大それたこと)を描き、学内技術探索と企業とのワークショップによって具体化し、講義後に具体的なアクションにつなげてもらうことを目指します。
- 院生は、自身の研究内容や技術知見を生かし、事業会社との関わりや実経営において求められるマネジメント知見のインプットを通じて産業課題を解くことにチャレンジし、EXIT(M&A・IPO)を見据えた実践的なアントレプレナーシップの習得を目指します。
-
特徴
全学連携・産学連携
- 中核協力企業(経営共創基盤、KDDI、東京大学協創プラットフォーム開発株式会社、松尾研究所)や著名起業家・科学者などによる講義と、研究室訪問や企業訪問を含むフィールドワークの複合型で進行します。
- また、本講座では、教員・受講生をつなぐ一定の専門知を持った学生TAを”Bridging Tutor”とし、受講生の学びを最大限生かすような体制を作っています。
ディープテックの起業モデルとグローバル市場を意識したカリキュラム
- 東京大学発、また日本国内のスタートアップの分野において、ものづくりや環境・エネルギー、素材といった分野は少ないのが現状です。そういった「工学部の本丸」ともいえる分野の起業モデルを確立するためには、高いレベルの技術開発的要素に加え、事業計画、資金調達やM&A・IPOといったファイナンス視点、社会ニーズの洞察など、求められる要素が多岐に渡ります。さらに、国内市場に閉じず、グローバル市場も見据えた視野の重要性は高まるばかりです。本講座では、上記の観点を踏まえたカリキュラムを設定しています。詳しくは講義詳細をご覧ください。
- 学生にとっては、研究を基に事業化するための知見を大学で学ぶことで、研究の社会実装のスピードやインパクトを高め、またキャリアの広がりをもたらすものと考えています。
フィールドワークを重視した設計
- 教室内の座学・グループワークにとどまらず、講義内での先端科学技術研究センター訪問を皮切りに、受講生には研究施設・企業・顧客候補・連携先候補への主体的な「フィールドワーク」の実施を奨励しています。
本講座修了後のフォロー体制・ベネフィット
- 修了証発行
- コミュニティ”DICE“(修了生のうち、優秀生対象。寄付企業、外部講師、メンター、起業家と繋がることができ、随時の起業相談、定期的な勉強会やイベント等を開催)への招待
- 成績優秀者への、各関心領域に応じた海外研修 等
-
体制
企画・監修

坂田 一郎
東京大学 工学系研究科 教授
/ 講座代表
松尾 豊
東京大学 工学系研究科 教授

田中 謙司
東京大学 工学系研究科 教授
カリキュラム・運営

村田 幸優
東京大学 坂田研究室

世羅 孝祐
シニアアドバイザー
東京大学 坂田研究室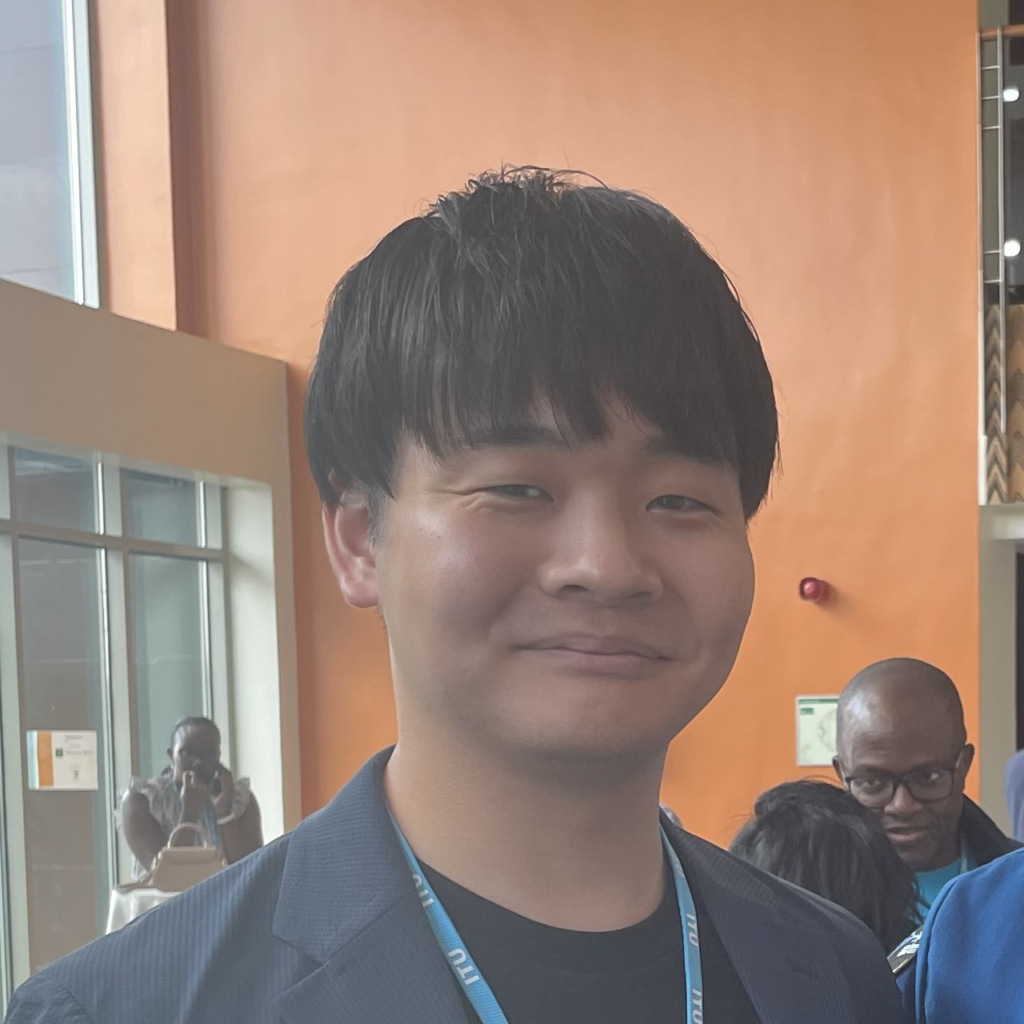
植竹 空
シニアアドバイザー
東京大学 坂田研究室
深津 幸紀
シニアアドバイザー
東京大学 坂田研究室中核協力企業

株式会社経営共創基盤

KDDI株式会社

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社

株式会社松尾研究所

記者会見(設立時 2021/8/18) -
受講生の声
本講座受講生の声をまとめています。こちらから是非ご覧ください。
-
コミュニティ-DICE
本講座修了生・フル聴講生は、学生間や企業との交流のみならず、有志勉強会、起業相談等、様々なイベントのあるコミュニティ”DICE”に参加が可能となります。詳細はこちら
-
修了生の活躍
本講座修了生の活躍をまとめています。こちらから是非ご覧ください。
本講座の動画公開について
講義動画の公開は、本講座公式YouTubeチャンネルより行います。
尚、本動画はメタバース工学部リスキリング教育工学プログラム「アントレプレナーシップ」でも活用しています。
メタバース工学部についてはこちらをご覧ください。


